こんにちは!看護楽しんでますか? SOUKI です!!!
今回は、特定行為研修を受講している際の1年間のスケジュールについて、学生目線でざっくり紹介してみたいと思います。
これから入学を考えている方や、現在入学しており、色々なタイミングで不安な方の参考になれば嬉しいです!
🌸4月:開講式と共通科目スタート
新年度が始まり、まずは開講式。
ここから「共通科目」と呼ばれる基礎的な授業がスタートします。
初めてのことも多くて不安もありますが、色々な病院の方々が入学してくるので、顔合わせになります。
開講してる施設の方は、知っている職場のスタッフが多い状況になると思います。
📚5月〜8月:共通科目+eラーニングで基礎固め
この時期は、座学だけでなく演習・実習を交えながら「共通科目」の内容を深めていきます。
同時に、eラーニングも進める必要があり、スケジュールは結構タイト。
授業もeラーニングが終了していないと受けることが出来ない授業もあるので、大変かもしれません。
でも、勉強の習慣がつく時期でもあるので、踏ん張りどころです。
🧪9月:共通科目修了試験
夏の終わりには「共通科目修了試験」があります。
試験の内容はeラーニングの最後にある確認テストより、同じ問題が出題されることが多いようです。
しかし、問題の内容は一緒でも、問題の順番が違います。テストはマークシートで行うことが多いです。
この試験をクリアすると、いよいよ次のステップ「区分別科目」へと進みます。
試験前はやっぱりピリピリしますが、仲間と協力して乗り切ります。
🧬10月〜12月:区分別科目に突入
10月からは専門性の高い「区分別科目」がスタート。
この時期もeラーニングや演習が続き、実践的な内容が増えてきます。
しかし、自分が選択した分野になるので、僕自身はとても楽しかった覚えがあります。
11月にはOSCE(客観的臨床能力試験)という、技術と対応力を評価される重要な試験もあります。
これは緊張しますね。僕もAline挿入テストの際に手が震えていました。💦
💉1月〜2月:実習+修了試験
年明けからは本格的な実習が始まります。
その前に2月には「区分別科目修了試験」もあるので、実習と勉強の両立がカギになります。
実習では、勤務している職場での実習となります。
現場の環境で学ぶことで、知識とスキルがグッと深まり、卒業後も即戦力として活動することが出来ます。
実習は1項目の特定行為(橈骨動脈ライン挿入 など)につき5症例の症例レポート作成が必要となります。また、追加で症例を経験した際には追加で症例レポートの記載が必要となります。
僕は60例以上のレポートを記載し、死ぬかと思いました。w
🎓3月:修了式
そして1年の締めくくり、修了式。
振り返ると、本当に内容の濃い1年だったと実感します。
ここまでの努力が次のステップにつながる、大切な節目になります。
1年間の流れを見ると、かなりハードに感じるかもしれませんが、特定行為研修は勤務を行いながら取得することが出来、実施に技術を重ねることで、その分成長も感じられる充実した時間となります。
如何でしょうか、これが簡単な特定行為研修の1年間の流れになります。少しでも皆さんの役に立てると幸いです。
ではまた!!!!
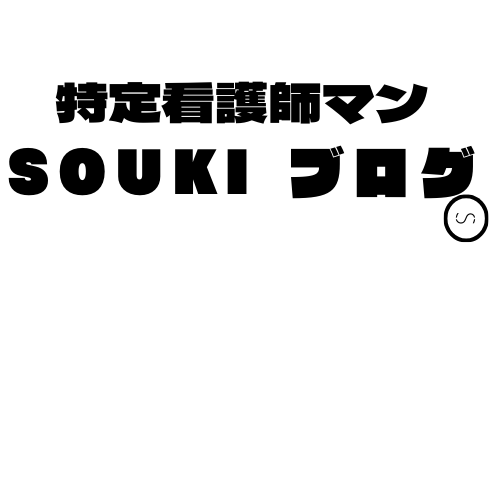
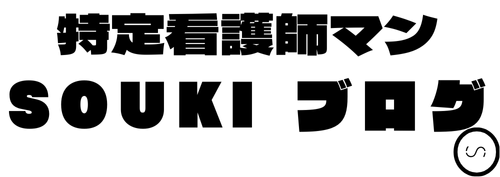
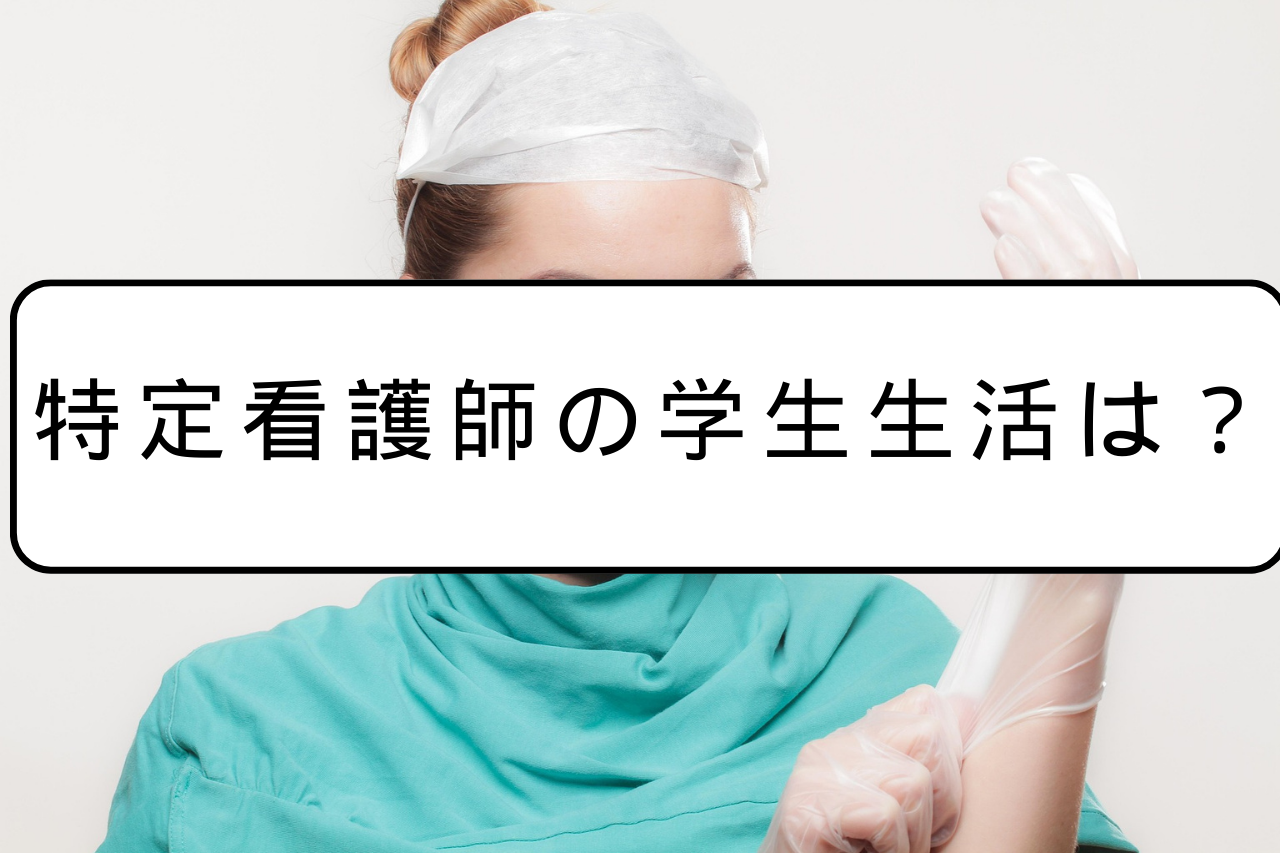



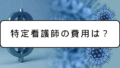

コメント