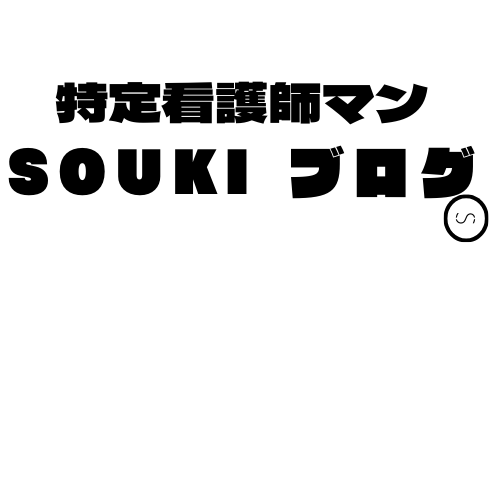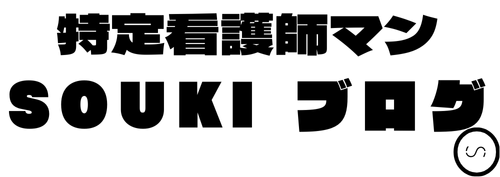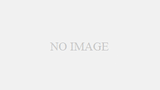【ICU看護】RASSスケールで迷わない!鎮静管理を安全に行うための実践ポイント5選
【ICU看護】RASSスケールで迷わない!鎮静管理を安全に行うための実践ポイント5選
ICUでの鎮静管理、「深すぎる?浅すぎる?」と悩むこと、ありませんか?
RASSスケールは、患者さんの鎮静レベルを客観的に評価する大切なツール。でも、実際の現場では「評価がブレる」「どう活かせばいいか分からない」と感じることも多いですよね。
この記事では、ICUナースがすぐに実践できるRASSスケール活用の5つのポイントを、わかりやすく解説します。
RASSスケールとは?ICUでの鎮静管理に欠かせない理由
RASS(Richmond Agitation-Sedation Scale)は、+4(興奮)〜−5(無反応)までの10段階で鎮静レベルを評価するスケールです。
ICUでは、「落ち着いていて刺激に反応できる」−2〜0あたりを目標にすることが多いです。
チーム全員がこの感覚を共有しておくと、鎮静深度のズレを防げます。
RASSスケールを使った鎮静管理の実践ポイント5つ
① 目標鎮静レベルは“なんとなく”で決めない
鎮静の目的(人工呼吸器との同調・安静保持・鎮痛など)を明確にし、
「今日はRASS −2を目指そう」と数値で具体的に設定することが大切です。
医師・看護師間で鎮静目標を共有しておきましょう。
② 数値だけじゃない、“雰囲気”も観察しよう
同じRASS−2でも、呼吸が荒い・表情がこわばるなど、鎮痛が不十分な場合があります。
鎮静=眠らせることではなく、苦痛を減らすこと。
呼吸・表情・体動なども一緒に観察しましょう。
③ 評価タイミングをそろえるのが信頼性アップのコツ
RASS評価は、刺激前→刺激後の反応の順で行うのが基本です。
同じ手順・タイミングで評価しないと、スコアが安定しません。
シフト交代時に「さっきはRASS−3で、刺激したら開眼したよ」と情報共有するだけでも、かなり違います。
④ 鎮静過多を防ぐ“減らす勇気”を持とう
深すぎる鎮静は、せん妄・離脱遅延・筋力低下の原因になります。
患者の安定を見ながら、少しずつ減量を提案できる看護師が信頼されます。
“必要最小限の鎮静”を意識するだけで、リハビリや離脱がスムーズになります。
⑤ チームで鎮静目標を共有する
鎮静管理は一人で完結するものではありません。
RASS評価の結果や鎮静の目的を医師・リハビリ・薬剤師など多職種で共有し、
「今日はこのくらいを目指そう」という共通認識を持つことが、患者さんの安全につながります。
まとめ:RASSスケールは“患者とつながるツール”
RASSスケールを使いこなすポイントは、評価を「数値」ではなく「状態の理解」に変えること。
鎮静レベルを定期的に見直し、チームで連携することで、患者さんにとってより安全で快適なケアが実現できます。
RASSは「鎮静管理の道しるべ」であり、患者さんと医療者をつなぐ“共通言語”です。
今日から、少し意識して使ってみませんか?😊
この記事で使った主なキーワード
- RASSスケール
- ICU 鎮静管理
- ICU 看護
- 鎮静スケール 使い方
- 鎮静 評価 看護師
この記事が参考になった方は、ぜひブックマーク・シェアをお願いします!